小中学生の学力を伸ばすカギは「学習習慣」!家庭で続かないときの具体的解決策

はじめに:なぜ学習習慣が大事なのか?
「うちの子、やる気があればできるのに…」
「勉強しなさいって言わないと全然やらない」
どの保護者のみなさんも、一度は感じたことがあるのではないでしょうか。
学力を大きく伸ばすカギは、特別な才能や有名塾の教材ではありません。
実は “毎日の学習を習慣にできるかどうか” こそが決定的な分かれ道になります。
能力の差より「習慣の差」
習慣がある子は、歯磨きのように当たり前に机に向かいます。反対に、習慣がない子は「今日は気分がのらない」と勉強を先延ばしにしがちです。この積み重ねが、学力・自信・将来の選択肢にまで影響します。
例えて言えば、習慣は“雪だるま”。
最初は小さい雪玉でも、毎日転がしていけばどんどん大きくなる。
一方で転がすのをやめれば、そこで成長は止まってしまいます。
今回の記事では、この「学習習慣をどう育てるか」を一緒に考えていきましょう!
この記事を書いた人![]()
学習塾・フリースクールSkip Study Base塾長
23年間、担任・教頭として学校に勤め、2025年に塾を開校。
これまでの経験と教育に対する思いを、目の前の子どもたちに注いでいます!
子どもが勉強を続けられない3つの理由
多くの子どもは、なぜ、勉強を続けられないのでしょうか。
それには、次の理由が考えられます。
1. 環境の誘惑が多すぎる
テレビ、スマホ、ゲーム…家には誘惑がいっぱい。机に向かっても、つい手が伸びてしまうのは自然なことです。
2. モチベーションの波に左右される
「やる気があるときだけやる」――これは非常に危険です。やる気は天気のように変わりやすく、待っていても安定しません。
3. サポート不足で挫折しやすい
わからない問題にぶつかったとき、誰にも聞けないと「もういいや」と投げ出してしまいます。
小中学生には“伴走者”が必要なことがよくあります。
きっと、どれも「確かに…」と、共感できる理由ばかりなのではないでしょうか。
つまり「意思が弱い」から勉強が続けられないのではなく、「環境が整っていない」だけなのです。
習慣化のしくみ:脳は「繰り返し」で楽をする
心理学では、新しい行動を習慣にするには 約66日 続ける必要があるといわれます。
これは、ロンドン大学の研究者による研究成果だそうです。
脳は繰り返し行動をすることで「考えなくてもできる回路」をつくります。
- 最初の2週間:抵抗期(面倒くさい・やりたくない)
- 3〜6週目:不安定期(やったりやらなかったり)
- 2ヶ月目以降:定着期(当たり前にできる)
これって、じつは筋トレと同じなんです。
「最初が一番きついが、続ければ楽になる」という法則があります。
私も多少、筋トレを続けているのですが、はじめたころは「めんどくさいな」「つらいから嫌だな」と思っていました。でも、1年も続けていると、反対にやらないとちょっと気持ち悪い、みたいな気持ちにすらなってきます。
家庭でできる!学習習慣を身につける5ステップ
ステップ1:時間と場所を固定する
「夕食後30分」「朝ごはん前に10分」など、時間と場所をセットにすると行動が自動化しやすくなります。
ステップ2:小さく始める
いきなり1時間は無理でも、5分なら始められる。習慣化のコツは「小さな成功体験を積むこと」です。
実は、この「とりあえず5分」はとても重要で、「やる気スイッチ」とも大きくかかわっています。
この話は、長くなりそうなので、また別のブログで紹介しますね。
ステップ3:見える化する
学習カレンダーやシールで「やった証拠」を残すと、子どもは達成感を得やすくなります。
ステップ4:親の声かけは“応援型”に
「やりなさい!」ではなく「続けられてるね」「昨日もできたね」と 肯定の言葉 をかけると、習慣は強化されます。
このとき、過剰に褒めないように注意してください。ここ、ポイントですよ!
ほめられたから、うれしくて勉強する!という外発的動機は、最初のうちこそいいものの、慣れてきてしまえば動機としては弱くなっていくでしょう。
それよりは、毎日続けている行動そのものを承認し、子ども自身が「続けられている自分っていいな」というふうに思えれば、それが自信となり、内発的な動機にもなると思います。
保護者の皆様は、ぜひ、声掛けのポイントにお気を付けくださいね。
ステップ5:一緒に環境を整える
勉強机の上をシンプルにする、スマホをリビングに置く――シンプルなことですけど、これだけで集中度は大きく変わります。
それでも続かない子に必要なのは「環境の力」
とはいえ、家庭での工夫にも限界があります。
- 兄弟の生活リズムが合わない
- 保護者が忙しく、毎日のサポートが難しい
- 子どもが反発してついつい言い合いになってしまう
こうした課題は、現代においてはどこのご家庭でも「あるある」というお悩みかもしれません。
では、どうやって解決するとよいでしょうか。
方法はいろいろあると思いますが、家庭以外の学習環境を利用することも有効な手段です。
「自習利用」が習慣化を支える
例えば、当塾では自習利用のサービスを提供しています。
これを、習慣化をサポートするものとしてご利用いただくことができます。
自習利用のメリットはこんなにある!
- 家では集中できない子も、教室に来れば自然と机に向かえる
- 講師の目が届くから「安心感」と「適度な緊張感」がある
- 周囲に勉強している仲間がいることで「自分もやらなきゃ」と思える
これはまさに「ジムに通う筋トレ」と同じ。
家で一人だと続かない運動も、ジムに行けば自然と体を動かせる。
それと同じように、塾の自習利用は“学習のジム”の役割を果たします。
学習習慣がつくと、子どもは勉強を“苦痛”から“日常”へと変えていきます。
その変化こそが、成績アップへの大きな近道です。
まとめ:習慣化の第一歩は「環境を変えること」
- 学力の差は「能力」より「習慣」の差
- 習慣は雪だるまのように積み重なり、やがて大きな成果になる
- 家庭で工夫しても限界があるときは、環境の力を借りることが効果的
👉 まずはSkip Study Baseの【体験授業】で、お子さまの学習習慣づくりを一緒に始めてみませんか?
公式LINEから簡単にお申し込みいただけます。



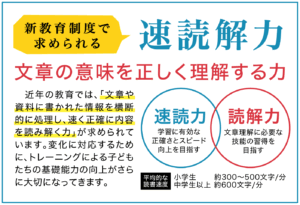
コメント