宿題にダラダラ1時間…本当は15分で終わる?家庭でできる学習習慣の整え方

「宿題を始めるまでに1時間。机に向かってはいるけれど、鉛筆が止まったまま。結局終わるのは寝る直前…。」
そんな姿を見て「どうしてうちの子は集中できないんだろう」とため息をついているお父さん、お母さんの様子。
これって「あるある」じゃないですか??
どうして、宿題を始めるまでに時間がかかるのでしょう?
どうして、机に向かったとしても、なかなか進まないのでしょう?
もちろん、学習が苦手、勉強の内容が分からない、ということが原因の一つとしてある場合も考えられます。
しかし、実は、宿題に時間がかかるのは能力不足ではなく、習慣や環境の問題であることもまた多くみられます。
正しい取り組み方を知れば、同じ宿題でも所要時間は1時間から15分~30分へと大きく変わります。
この記事では、家庭でできる「宿題を短時間で終わらせる習慣づくり」の具体的な方法をお伝えします。
この記事を書いた人![]()
学習塾・フリースクールSkip Study Base塾長
23年間、担任・教頭として学校に勤め、2025年に塾を開校。
これまでの経験と教育に対する思いを、目の前の子どもたちに注いでいます!
宿題に時間がかかる本当の理由
子どもはゴールをイメージしないまま机に向かっている
子どもたちを見ていてよくあるパターンは「やってみたら、案外めんどくさくなかった」「思ったよりも早くできた」というものです。これ、宿題も同じだと思うんですよね。
つまり、宿題をやる前に「どんな順番でやっていったらいいだろう?」「これを自分がやったら、どれくらいの時間がかかるだろう」というゴールのイメージや、ゴールまでの過程のイメージを考えられていないのです。
そうすると、漠然と
「(なにからやったらいいか考えたくないから)宿題やりたくない」
「(どれくらい時間がかかるか分からないから)めんどくさそう」
などという思考になっていきます。
そのため、机に向かうまでになかなか動き出せず、他の楽なこと(ゲームや遊び)に逃避します。
また、机に向かっても「何から始めよう」と迷い、最初の一歩に時間を取られてしまいます。
「集中が続かない」のは能力ではなく環境の問題
机に向かって、学習を始めたとしましょう。
集中できなくて、5分もしないうちに、よそ見、手が止まる、おしゃべりしだす…
こうしたことは性格や能力ではなく、環境の影響が大きいのです。
テレビの音、スマホの通知、兄弟姉妹の話し声…。
こうした刺激があると、どうしても注意が途切れてしまいます。
いまから30分、いまから1時間、学習するぞという環境を保護者主導で整えられるといいですね。
親の声かけや家庭のルールが無意識にダラダラを助長している
「まだ宿題終わらないの?」
「早くやりなさい」
良かれと思って、こんな声を掛けてしまいます。
大人にもいろんな都合がありますし、ついつい言っちゃいますよね。
この記事を読んでいただいている多くの方はきっとすでにご承知のことと思いますが、こうした声かけは逆効果になることがあります。
プレッシャーで余計に手が止まったり、「どうせ自分なんて」と気持ちがマイナスになったりして、結果として宿題が長引いてしまうのです。
宿題が15分で終わるようになる家庭習慣のポイント
時間を「区切る」ことで集中が生まれる
人の集中力は長く続きません。大人でも20分が限界だと言われています。
かく言う私も、集中力が続かない性質です。だからこそ、時間を決めてある程度取り組んだら休憩して、リフレッシュをします。
ですので、「15分だけやってみよう」と時間を区切ることが効果的です。
制限時間があると、子どもはゲーム感覚で集中できます。
または、その子に合った適切な分量をいったんのゴールとし、区切りを付けながら宿題を進めるのもよいと思います。
見通しを「可視化」する(今日のゴールを明確に)
「今日は算数ドリル2ページ」「漢字5行」など、具体的なゴールを最初に明示することが大切です。終わりが見えないと子どもは不安になりますが、ゴールがはっきりしていれば安心して取り組めます。出されている宿題の量を保護者の方が一緒に確認してスタートをしてみるようにしましょう。
たったこれだけの声掛けで、お子様の取り組みが少し変わるかもしれませんよ。
成功体験を「振り返る」ことで習慣化が進む
「15分でここまでできたね!」
「昨日より速くできたね!」
と成果を振り返ることで、子どもは自己効力感を得ます。
小さな成功を積み重ねることが、習慣化の第一歩になります。
できたことをたくさん承認してあげてください。
気を付けていただきたいのは、「親にとって都合のよい行動をしたから褒める」のではありません。
今日からできる!家庭での具体的な取り組み
すでに実践されているかもしれませんが、ぜひ遊び感覚で試してみてください。
上手くいけばラッキー!
うまくいかなかったら、また別の手を試してみる。
こんなマインドで進めてくださいね。
15分タイマー法:短時間集中を“ゲーム感覚”で
キッチンタイマーやスマホのアプリで15分をセット。
「よーい、スタート!」と声をかけると、子どもは一気に集中します。
終わったら2〜3分休憩を入れて、次の15分にチャレンジしましょう。
宿題チェックリスト:終わったらすぐに視覚的にわかる仕組み
紙やホワイトボードに宿題の項目を書き出し、終わったらチェックを入れるだけ。
達成感が視覚的に分かるので、モチベーションが続きます。冷蔵庫やリビングに貼って、家族で共有するとさらに効果的です。
また、1週間分の宿題チェックリストを作って、毎日の達成を可視化していくのもモチベーションにつながるでしょう。
大人の声かけ、言い換えパターン
- NG:「まだ終わってないの?」
- OK:「あと何分で一区切りつけようか?」
- NG:「早くやりなさい」
- OK:「今から15分だけ一緒にやってみよう」
声掛けをちょっと変えるだけで、雰囲気はだいぶん変わります。
プラスの気持ちで子どもを動かす声掛けを考えたいですね。
自習スペースづくり:テレビやスマホの誘惑を断つ
リビング学習でもOK。
ただし机の上には教材以外は置かない、テレビやスマホは手の届かない場所に置く。
たったこれだけで集中度は一気に変わります。
また、最初にお子さんと宿題をする時の約束を確認しておくのもいいですね。
skip study baseでの取り組み
短時間集中を繰り返す“トレーニング”
私たちの塾では「短時間集中」を毎回の授業で実践しています。
子どもたちには休憩することの大切さを伝えています。
タイマーを活用したり、集中→休憩→集中のリズムをつくったりすることで、子どもは勉強を「やらされるもの」から「自分で進められるもの」へと変えていきます。
実際、多くの子が、集中が切れてきたり1コマ終わったりすると自分で「休憩してきます」といってリラックスエリアに行きます。その後、自分で席に戻ってきて続きの学習をしたり、次の教科の学習をしたりしています。
こうしたセルフコントロールができるようになることは、とても良いことだと思っています。
「見通し」と「振り返り」
skip study baseでは、毎回の授業「今日は何をやるか?」を子どもと指導者が会話して確認します。子ども自身が「自分がやらなけらばいけないと考えていること」や「やるべきこと」を明確にするのです。また、定期的に学習の振り返りをして、これまでの学習がどうだったか、テスト勉強はうまくいったか、などを確認します。
これにより、子ども自身が、自己の学習に対する理解度を深めていき、習慣化につなげたいと考えています。
塾に通うメリット、それは…
ずばり、「親子バトルからの解放」です!
家庭で「宿題やった?」「早くしなさい!」と声を荒げる必要はありません。
塾に通うことで、保護者の方の負担を減らすことができれば、穏やかな声掛けを意識して増やしていくことができるのではないでしょうか。そして、承認の声掛けを増やしていけば、子どもたちの自己効力感をさらにのばしていくことができます。それは、ご家庭でこそやる意味があるのです!
まとめ:宿題時間を短縮すると子どもが変わる
宿題がダラダラ続くのは、能力のせいではなく環境と習慣の問題です。
時間を区切り、見通しを持ち、成功体験を積み重ねることで、宿題は驚くほど短時間で終わるようになります。
ダラダラが減れば、子どもの自己効力感も上がります。
「学習習慣の定着」は点数アップだけでなく、子どもの未来につながる大切な力です。
そして、そのサポートを専門的に行っているのがskip study baseです。
「うちの子も短時間で集中できるようになってほしい」
「親子バトルを減らしてプラスの声掛けを増やしたい」
そんな思いをお持ちの方は、ぜひ一度体験授業にお越しください。
👉 体験授業・ご相談は公式LINEからどうぞ



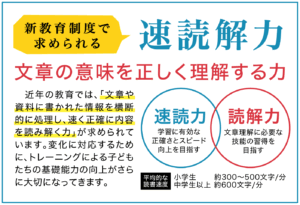
コメント